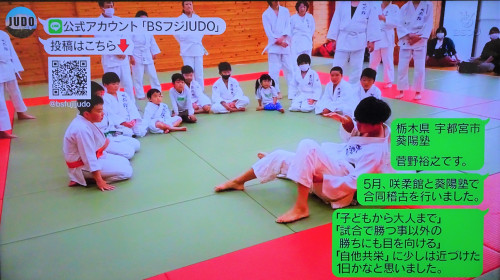おしらせ
2023-07-18 14:50:00
🌻8月の稽古予定🌻
いつも咲柔館ホームページをご覧になってくださりありがとうございます!
8月の稽古予定を掲載いたします。
より画像が鮮明な「PDFファイル」版はこちらです。
↓
![]() カレンダー 2023年8月.pdf (0.23MB)
カレンダー 2023年8月.pdf (0.23MB)
【お知らせ】
①夏期休館日
8/13(日)~16(水)は夏期休館日となっております。
該当する曜日に通われているお子様に関しましては、お手数をおかけしますが振替をご利用ください。
②子どもクラス&中高生・大人クラス 合同稽古
8/11(金・祝)に両クラス合同稽古を実施いたします。柔道を通じ、世代を越えた交流を楽しみましょう!ぜひ、ご参加ください。 
【時間】
10時~12時45分
※子どもクラスは11時30分まで
【場所】
栃木市総合体育館 柔道場
※栃木市総合運動公園HP
⇩
https://tochigi-park.com/
【集合時間・場所】
9時40分・栃木市総合体育館内 受付付近
【参加お申し込み方法】
子どもクラス
→振替制度をご利用し、8月7日(月)までにメール・お電話にてお申し込みください。
中高生・大人クラス
→8月10日(木)までにメール・お電話にてお申し込みください。
※この日も入塾をご検討されている方の「見学」は受け付けております。下記よりお申し込みください。
⇩
https://shojukan.com/contact
咲柔館は、お子さんから大人の方まで、初心者の方やブランクがある方でも柔道を楽しめる道場です。柔道にご興味がある方は、お気軽にお越しください。
見学・体験のお申し込みはこちらからお願いします。
↓
https://shojukan.com/contact
それでは、8月もよろしくお願いいたします。


2023-07-12 10:55:00
📝コラム「乱取りの中にも自他共栄の心を~全力でも8割、思いやり2割~」(両クラス)

咲柔館コラム237
乱取りの中にも自他共栄の心を~全力でも8割、思いやり2割~
反復練習で磨いてきた技をお互いが自由にかけ合う「乱取り」。立技、寝技ともに乱取りが好きな塾生様は、子どもクラス、中高生・大人クラス共に多く、最近は少しずつ本数を増やしています。乱取り中の攻防はとても面白く、日常生活の中にはない興奮を味わうことができます。
ただ、乱取りをする上で最も大切なのが「安全性」です。咲柔館では、「怪我をしない、怪我をさせない柔道」を常に心がけ、勝敗に拘泥しすぎずに、「お互いが笑顔で終えられる乱取り」の実践を目標にしています。“安全第一 おもしろ第二”(糸井重里)です。

乱取りで大切にしていることは2つです。
1つ目は、潔く受身をとること。稽古中の受身は負けではありません。再び立ち上がるための立派な技術の1つです。「きれいな受身はかっこいい」。この価値観をしっかりと浸透させていきたいと思います。
2つ目は、安全に相手を投げること。強引な力まかせの技ではなく、理にかなった技で投げる。投げた後は相手の袖を引く。こうした技術をしっかりと身につけ、意識せずとも実践できるようにしなくてはいけません。
これら2つのことは、反復練習を何度も繰り返し、体に染みこませることが大切です。ただ、いざ乱取りが始まると夢中になってしまい、ついつい我を忘れてしまうことも…。そこで乱取り前にお伝えしている合葉が「全力でも8割・思いやり2割」です。
真剣勝負の中にも「自他共栄」の心を持てるのが、真の柔道家です。相手がいてこそ自分を高めることができます。心と体に相手を思いやる余裕を持ち、力まずに、肩の力を抜いて乱取りを行うことが大切です。余計な力を抜くことは、より良い技や受身にもつながります。
柔道で相手を投げたり、抑えたりすることが暴力になってはいけません。稽古の前後にしっかりと礼をし、お互いに敬意を持って乱取りを行ってこそ、共に高め合う柔道であり得るのです。相手を大切にする気持ちで乱取りをすれば、自ずと稽古をする度に信頼や友情が深まっていきます。柔道をすることで、仲が良くなる。そんな柔道をこれからも追究、実践し続けたいと思います。
〈お知らせ〉
「安全で楽しい乱取りの実践」を目標とした「子どもクラス&中高生・大人クラス合同稽古」を7月29日(土)に行います(@栃木市総合体育館)。5月に引き続き、葵陽塾(きようじゅく)様(宇都宮市)もご参加される予定です。前回は、5歳から70代の方まで約30名で楽しく稽古をすることができました。「生涯柔道」や「文武一道塾 咲柔館」にご興味がある方のご見学等も受け付けております。
詳しくはこちらをご覧ください。
⇩
https://shojukan.com/info/5220572
「柔道家が増えることで、社会はより良くなる」
文武一道塾 咲柔館
※「note」より転載
https://note.com/shojukan/n/n9a411ab45dc2
2023-07-11 11:45:00
昇級・昇段への道しるべ(中高生・大人クラス)
10月1日(日)に行われます「昇級・昇段審査会」(@県南体育館/小山市)に向けて「昇級・昇段への道しるべ」を作成いたしました。昇級・昇段審査会に至るまでの過程と費用などを記載してあります。昇級・昇段にご関心がある方はご確認ください。
⇩
![]() 昇級・昇段への道しるべ(日程・費用).pdf (0.12MB)
昇級・昇段への道しるべ(日程・費用).pdf (0.12MB)
※以下、PDFファイルと同内容です
昇級・昇段への道しるべ
10月1日(日)審査会用
【昇級・昇段審査会 内容】
・2級
礼法、受身
・1級
試合(3分×4試合程度)、形(3種類)
・初段
試合(3分×4試合程度)、形(9種類)
【文武一道塾 咲柔館 審査会許可の目安】
①週1回程度の稽古を概ね1年半以上継続している。
②咲柔館の「審査会許可試験」に合格している。
〈審査許可試験〉
①礼法
②受身
③打ち込み・投げ込み
④形
⑤乱取り(3分×5本程度)
⑥柔道に関するレポート(800字程度)
※級・段ごとに内容は異なります。
【昇級・昇段審査会までの流れ】
①参加意志をお伝えください(稽古時・メール・電話) 7月22日(土)まで
↓
②咲柔館の「審査会許可試験」を受けてください。
実技
8月5日(土)・12日(土)のどちらかの稽古内
※両日共にご参加できない場合は別日程をご提案します。
レポート
8月26日(土)までにご提出(メールにて)
↓
③合格された方は、「全日本柔道連盟への登録」と「試合用の柔道衣の購入」をしていただいます。
〈全日本柔連連盟登録料〉
社会人:4,200円
大学生:3,900円
高校生:3,600円
中学生:3,400円
※現金にてお支払いください。
〈試合用の柔道衣〉
15,000円程度(刺繍・ゼッケン込み)
※注文後、柔道衣業者へお振り込みください。
↓
④週2回以上を目標に稽古を継続してください。
↓
⑤10月1日(日)の試験に臨みましょう。
〈審査料〉
・2級… 2,000円
・1級… 2,500円
・初段…25,500円
昇級・昇段の目的は、審査会への準備、当日の試験を通した心技体の成長です。昇級・昇段をすると帯の色が変わります。ただ、最も大切なのは目に見えない部分の変化です。審査会に参加される方には、しっかりとサポートをいたしますので、己を一歩ずつ成長させ、各級・段にふさわしい実力をつけましょう。
※昇級・昇段を目指さなくても(白帯のままでも)稽古をすることの価値は変わりません。審査会への参加に関しましては、ご自身のお気持ち・体力やご家庭や学業・お仕事のご都合等を考慮してお決めください。もし、参加するかどうか迷っているなど、ご相談がございましたらお気軽にお声かけください。




2023-07-07 10:12:00
📝コラム「『動の稽古』と『静の稽古』~気持ちを切り替える練習~」(子どもクラス)

咲柔館コラム236
「動の稽古」と「静の稽古」~気持ちを切り替える練習~
お子さんたちはいつも元気一杯。動くことが大好き。休憩時間でも、誰かの「オニごっこしようよ~!」の一言で「ワ~!」と大きな声を出して遊び始めます。時には、稽古メニューが全て終わった後に「先生、〇〇をもう1回やろうよ!」と言うことも。ヘトヘトになっても、少し休めばまた元気になって動きまわれる子どもの体力って本当にすごい!
体を目一杯動かす「柔道遊び」「受身・技の練習」といった“動の稽古”と同じくらいに、咲柔館では“静の稽古”も大切にしています。例えば「礼法」です。早く動きたい、相手と組みたい、という気持ちがあったとしても、必ず稽古前には一旦心を落ち着けて礼をする。どんなに疲れていても、稽古後にはしっかりと礼をする。こうした礼法をお子さんたちにも徹底しています。他にも「黙想」「古典の素読」「絵本の読み聞かせ」「稽古の振り返りノート記入」「学校・塾の宿題」「着替え」「片付け」など、心静かに1つのことに打ち込む場面も沢山設定しています。未就学児・小学校低学年のお子さんたちでも、こうした“静の稽古”を2~3ヶ月続けると少しずつ落ち着いた行動がとれるようになってきますよ。
思いっきり体を動かしたり、声を出した後は、静かな場面への切り替えがスムーズにできるようになります。例えば、宿題への集中度を稽古の前後で比較してみると、明らかに稽古後の方が黙々と学習に取り組めるお子さんが多いように感じます。最近、この事に関する興味深いTwitterを見つけました。
思い切りふざけて大騒ぎすると、その後は自然に静かな時間がやってきます。この時、脳内でとてもよいことが起きます。大騒ぎしてふざけることで脳の扁桃体が満足し、静かに過ごすときは前頭前野が扁桃体を抑制します。この切り替えの経験をたくさんすると扁桃体と前頭前野をうまく使う力がつき、扁桃体が司っている怒りの感情も管理できるようになります。これがキレない子です。反対にふざけたり大騒ぎしたりするのを常に抑えつけていると、切り替えの経験ができません。扁桃体と前頭前野を管理する力がつかず、怒りなどの感情も抑制できないままキレやすい子になってしまう可能性があります。
親野智可等(教育評論家)公式Twitterより(2023年6月28日)
⇩
※https://twitter.com/oyanochikara/status/1673994760359661568
なるほど!脳の扁桃体と前頭前野が深く関係していたのですね。とても勉強になりました。この他にも、親野先生がもう少し詳しく解説されている資料もWeb上にありましたので、ご興味がある方は併せてご覧ください。
⇩
Benesse ホームページ内
ベネッセ教育情報
「ふざけてばかりだとけじめのつかない子になる? [教えて!親野先生]
https://benesse.jp/kosodate/201609/20160927-1.html
もちろん、思いっきり体を動かした後は、必ず静かな時間を過ごせる、という訳ではありません。でも、こうした“動の稽古”と“静の稽古”の切り替えを繰り返す中で、お子さんたちは、少しずつけじめある言動をとれるようになってきました。思いっきり楽しむ稽古、静かに集中する稽古、その両方をうまく組み合わせながら、これからもお子さんたちの心の成長をゆっくり、じっくりサポートしていきたいと思います。
「柔道家が増えることで、社会はより良くなる」
文武一道塾 咲柔館
※「note」より転載
https://note.com/shojukan/n/n7d162db693ae
2023-07-06 10:22:00
咲柔館が(ちょこっと)テレビに出ました※7月8日(土)に再放送あります
7月1日(土)、「JUDO」(BSフジ)の投稿コーナーで、5月に実施した「子どもクラス&中高生・大人クラス合同稽古」の様子が放送されました(約30秒)。稽古に来てくださった葵陽塾(きようじゅく)代表の菅野先生が投稿してくださったそうです。菅野先生ありがとうございます!
再放送もございますので、ぜひご覧になってください。
〈再放送日時〉
7月8日(土)9時30分~10時1分
BSフジ ホームページ
⇩
https://www.bsfuji.tv/judo/pub/index.html
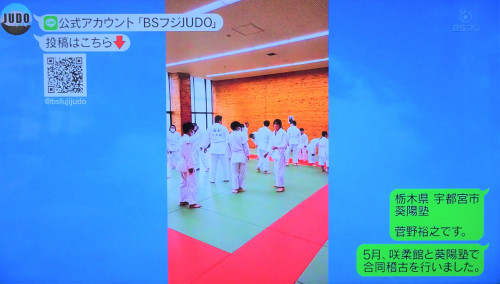

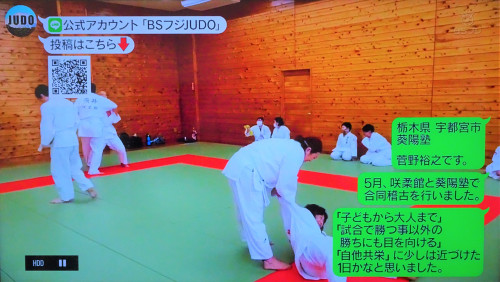

7月29日(土)の子ども&中高生・大人クラス合同稽古にも葵陽塾様がいらっしゃる予定です。ぜひ、ふるってご参加下さい。
※入塾をご検討されている方の見学も受け付けております。お気軽にお申し込みください。
詳細・見学のお申し込みはこちらからどうぞ
⇩
https://shojukan.com/info/5220572