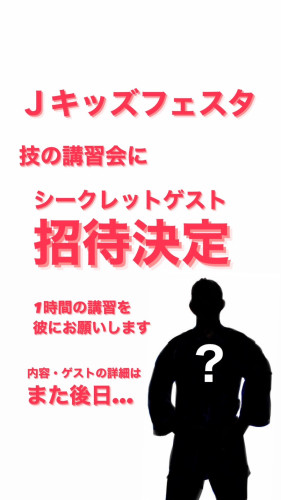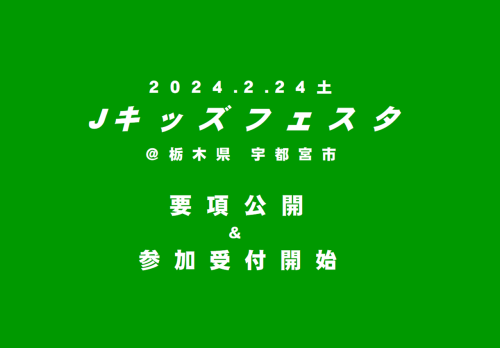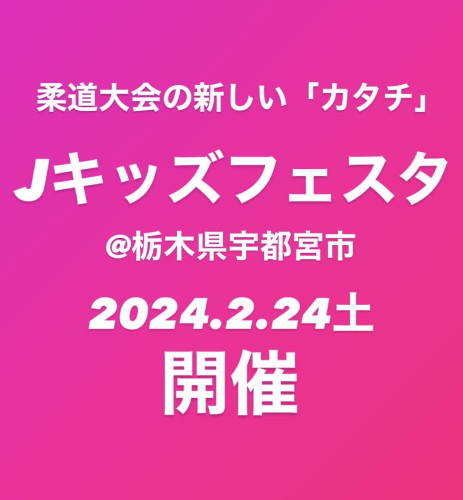おしらせ
2024-01-05 12:37:00
「Jキッズフェスタ」(子ども柔道イベント) シークレットゲストが来ます!
子どもたちが「柔道って面白い!」「柔道を続けたい!」と思えるようなイベント「Jキッズフェスタ」を2月24日(土)に開催します。
昨年末のお申し込み開始から現在に至るまでで20名ほどのお子さんからお申し込みをいただいております。
以下、充実のラインナップです!
①柔道遊び・ACP(アクティブチャイルドプログラム)体験
②親善試合(未就学児〜小学生)
③柔道クイズ大会
④技の講習会
⑤乱取り
おまけ(事前提出された柔道川柳の表彰)
※時間は9時~16時を予定
※会場はユウケイ武道館(栃木県宇都宮市)
なんと、④技の講習会では「シークレットゲスト」に来ていただくことが決まりました!ゲストの詳細や講習内容については近日公開!
ぜひJキッズフェスタにご参加下さい!中学生・高校生のご参加もお待ちしております。
※申し込み期限まであと「26日」
2023-12-31 15:43:00
📝咲柔館は“年中夢求”
咲柔館コラム262
咲柔館は“年中夢求”
12月29日(金)、今年最後の稽古を無事に終えることができました。今年も大きな怪我がなく全ての稽古を行うことができ、ほっとしております。
2023年も沢山のご縁をいただき、12名の方が咲柔館に入塾してくださいました。子どもクラスは新しい仲間が増え、今まで以上に元気一杯に柔道を、一所懸命に学習を行っています。中高生・大人クラスには、「柔道をやりたかったけど、やれる環境が見つからなかった」という方々が多くご入塾されました。そういった方々に柔道を一から学ぶ環境をご提供できたことを本当に嬉しく思っています。
年末年始はゆっくりと過ごしたい所ですが、私は柔道の技を身につけたり、仕事を進めることにおいて、今年の干支「ウサギ」ではなく、明らかに「カメ」なのです…。まだまだやるべき事務処理が残っていますし、来年の下準備としてやりたいことも山積しています。
家族との時間を最優先しつつ、今年の道場運営・経営の振り返りや残務処理、来年の稽古・イベントの下準備を進めます。咲柔館は、「柔道家を増やすことで社会をより良くする」という夢に向かって“年中夢求”です。
来年2月には、子ども柔道イベント「Jキッズフェスタ」を開催します。お子さんから大人の方まで、会場に来られた皆さんが柔道を楽しめる、学べるイベントになるよう、共催の葵陽塾様と力を合わせ、しっかりと準備してまいりますので、楽しみにしていてください。
来年は、干支の「辰」のように天に昇る勢いで道場運営・経営を進めます…と言いたい所ですが、やはり私は自分らしく地に足をつけて、1歩ずつ前に進みたいと思います。
塾生の皆さま、保護者の皆さま、ホームページやSNS等で咲柔館の発信をご覧になってくださった皆さま、今年も大変お世話になり、ありがとうございました。どうぞ素敵な年末年始をお過ごしください。来年もよろしくお願いいたします。
※2024年の稽古は1月5日(金)よりスタートです
「柔道をやることで、人生はより豊かになる」
「柔道家が増えることで、社会はより良くなる」
文武一道塾 咲柔館
2023-12-28 11:37:00
📝子どもも大人もみんなが笑顔になる稽古(両クラス)
咲柔館コラム261
子どもも大人もみんなが笑顔になる稽古
12月23日(土)、今年最後の「子どもクラス&中高生・大人クラス合同稽古」を行いました。この合同稽古は、普段顔を合わせない両クラスが交流できる場を作りたくて、今年からスタートしました。
中高生・大人の方も「先生役」ではなく、子どもと一緒に全てのメニューを行うのがこの合同稽古の特徴です。みんなが最後に1本の列車になる「じゃんけんトレイン」、好きな動物に変身して全力で疾走する「アニマルリレー」、相手のバランスをくずして倒す「バランス受身」など、技の練習以外もみんなで楽しく体を動かしました。大人の方の中には、「お子さんたちと全力で遊んでいる時の方が、柔道より疲れるかもしれないですね。」と笑顔で話されている方もいらっしゃいました。

じゃんけんトレイン①
じゃんけんトレイン②
バランス受身
立技の練習
寝技の練習
そして、今回はスペシャルゲストとして、筆を使わない“ハンドドローイング墨絵師”の荒川颼(しゅう)先生が稽古の見学に来られました。以前から柔道にご興味があったそうで、あの古賀稔彦先生をモデルとした作品を持って来てくださいました。塾生の皆さんは指や手で描いた迫力ある作品をご覧になり、とても感動されていたようです。やはり、素晴らしい芸術作品に触れると心が動きますね。
荒川先生の作品は、Instagram等でもご覧になれます。唯一無二の作品をぜひご覧ください。


古賀先生とモデルとした作品
塾生の皆さんのプレゼントをくださいました!

荒川先生Instagram
⇩
https://www.instagram.com/godloveyou1204/
今回の稽古には6歳から70代の方までが参加されました。世代を越えて「組み合う」「競い合う」「語り合う」そして「笑い合う」、そんな笑顔いっぱいの稽古でした。来年もみんなが笑顔になれる合同稽古を続けていきたいと思います。
今年も残りわずかとなりました。寒い日が続きますが、柔道で心と体を温めて乗り切りましょう。なにかと慌ただしい時期ですが、健康に留意され充実した年末をお過ごしください。
「柔道をやることで、人生はより豊かになる」
「柔道家が増えることで、社会はより良くなる」
文武一道塾 咲柔館
※「note」より転載
https://note.com/shojukan/n/ndba62c03cadb
2023-12-26 10:04:00
子ども柔道イベント「Jキッズフェスタ」 参加受付開始
【Jキッズフェスタ】は、子どもから大人までが「柔道っていいなあ~」としみじみ感じていただけることを目標とした「生涯柔道普及イベント」です。
いよいよ要項を公開し、参加受付もスタートします。「参加してみたい!」と思ってくださった方は、お気軽にお申し込みください。
※文武一道塾 咲柔館のお子さまは、申し込み手続きに関しまして直接お伝えいたします。
【申し込みまでの流れ】
①要項を確認
![]() Jキッズフェスタ 要項.pdf (1.05MB)
Jキッズフェスタ 要項.pdf (1.05MB)
⇩
②Jキッズフェスタ参加申し込み(エクセルファイル)を入手
〈入手方法〉
文武一道塾 咲柔館にメールをし、「Jキッズフェスタ参加希望」の旨をお伝えください。受信後、参加申し込み(エクセルファイル)をお送りいたします。
咲柔館メールアドレス:shojukan_judo_tochigi@yahoo.co.jp
※受信後、ご返信をいたします。もし、3営業日以内に返信がない場合、セキュリティーの関係でメールが届いていない可能性があります。その際は、お手数をおかけしますが、お電話でご連絡ください。
咲柔館 電話番号:070-4330-5718
火~土 9時~18時(祝日・年末年始を除く)
もしくは
葵陽塾ホームページより直接ダウンロードしてください。
↓
https://kiyojuku-judo2021.wixsite.com/my-site
⇩
③申し込みデータを下記アドレスまで送信
咲柔館メールアドレス:shojukan_judo_tochigi@yahoo.co.jp
※受信後、ご返信をいたします。もし、3営業日以内に返信がない場合、セキュリティーの関係でメールが届いていない可能性があります。その際は、お手数をおかけしますが、お電話でご連絡ください。
咲柔館 電話番号:070-4330-5718
火~土 9時~18時(祝日・年末年始を除く)
園や学校の運動会、習い事の発表会のような和やかで穏やかな感じの運営を心がけたいと思っています。Jキッズフェスタに関しまして、何かご質問等ございましたらお気軽にご連絡ください。皆さんと会場でお会いするのを楽しみにしております。
☆Jキッズフェスタまであと「59」日
※申し込み締め切りまであと「36」日
【文武一道塾 咲柔館×葵陽塾=Jキッズフェスタ実行委員会】
2023-12-26 09:57:00
子ども柔道イベント「Jキッズフェスタ」 主なプログラムのご紹介
「Jキッズフェスタ」は、お子さんたちが生涯にわたって柔道を「する」「観る」「支える」「学ぶ」「楽しむ」、そんな「柔道家」「柔道ファン」になっていくことを目的とした「生涯柔道普及イベント」です。
※「J」は、柔道家(JUDOKA)・治五郎(JIGORO)・自他共栄(JITAKYOEI)の頭文字
【主なプログラム】
①親善試合(未就学児・小学生対象)
→学年や体重に加え、柔道経験・技量に合わせてカテゴリー分けをし、更に安全面に配慮した「特別ルール」で行います。柔道経験が短い、試合に出たことがないお子さまにおすすめです。1人2試合程度行います。
(例)寝技のみ部門・足技のみ部門 など
②柔道遊び
→柔道の動きを使った楽しい遊びを沢山行います。運動が少し苦手なお子さんでも楽しめるメニューです。
③柔道クイズ
→柔道の技や歴史などに関するクイズを通し、柔道を深く理解します。「えっ、そうだったの!」という新発見があるかも!?
この他に「技の研究タイム(講習)」・「みんなで乱取りタイム」などもあり、未就学児、小学生、中学生、高校生が1日をかけて一緒に柔道を学び、楽しめるプログラムをご用意しています。
ご興味を持ってくださった方々から個別に「参加してみたいです!」とご連絡をいただきとても嬉しいです。皆さんと会場でお会いするのを楽しみにしております。
☆Jキッズフェスタまであと「59」日
【文武一道塾 咲柔館×葵陽塾=Jキッズフェスタ実行委員会】